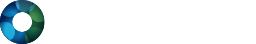印刷博物館
- 凸版(活版印刷)
- グラビア印刷(凹版印刷)
- フレキソ印刷
- 孔版(シルクスクリーン印刷)
- 平版(オフセット印刷)
- オンデマンド印刷
- 高精細印刷
- コロタイプ印刷
- ハイファイ印刷
- ダブルトーン印刷
- セキュリティ印刷(コピー防止)
- 電子透かし印刷(コピー防止)
- スクラッチ印刷
- UVインキ印刷
- 蓄光インキ(光る印刷)
- フォトクロミック印刷(光る印刷)
- ラメ印刷(光る印刷)
- パール印刷(光る印刷)
- 蛍光インキ(光る印刷)
- フロッキー印刷・植毛印刷
- 芳香印刷(マイクロセント)
- 示温印刷(発砲印刷)
- バーコ印刷(発砲印刷)
- レンチキュラープリント(立体印刷)
- 3Dホログラム(立体印刷)
- クリヤー印刷(光沢を出す)
- ニス引き(光沢を出す)
- プレスコート(光沢を出す)
- PP貼り(光沢を出す)
- 圧着加工
- 型押し
- 箔押し
- 空押し
- エーデルグラム(コピー防止)
- 点字印刷
- グーテンベルグと科学革命
- 科学ジャーナルの誕生
- これからの科学ジャーナルのゆくえ
凸版(活版印刷)
ハンコや版画と同じ原理のため、版の形状は側面から見て凸状になっています。印刷される部分がされない部分よりも一段高くなっていてインキを凸面に付けて紙をのせ、上から圧力をかけることによって直接紙に印刷されます。凸版印刷には鉛版(えんばん)や樹脂版に電鋳版(でんちゅうばん)などがあり、活版印刷とも呼ばれています。木版刷りが1枚の板からできているのに対して、活版印刷の場合は文字が一文字ずつ活字でできており組み終わった文字は印刷後バラバラに戻して再度別の版で利用されます。
この鉛の活字は1430年にヨーロッパで発明されており、それ以前の1410年頃にフランス国内で実用化されていた印刷用のインキを使って、1455年にドイツのヨハン・グーテンベルグが、広い面積に平均して圧力を加える工夫として葡萄やオリーブ油を絞るプレス機を応用することで機械化した印刷技術を発明して聖書を印刷したことが本格的な印刷時代の幕開けとされています。
現在でも、例えば平滑度の低いザラ紙を使うマンガ雑誌などには、平版よりも刷版に凹凸のある活版の方が印刷に安定しており、耐刷性にも優れることから樹脂凸版が主に使われています。この樹脂凸版とは、紫外線露光などで性質が変化する高分子物質の感光性樹脂を刷版に用いた印刷になります。他にも、段ボールに印刷するゴム凸版や、近年環境への配慮から注目が集まっているフレキソ印刷も包装関連を中心に活躍している凸版印刷の一種と言えます。
グラビア印刷(凹版印刷)
グラビアは凹版印刷の一種で、細かい凹点(グラビアセル)内に詰められたインキの量によって濃淡を表現します。版の窪んだ部分にインキをためて、それを圧胴の圧力でインキを転移させて印刷します。
特徴としてはインキを載せ転移させる量が一定であるという計量精度に優れています。1インチあたり何本セルが入っているかというスクリーン線数にもよりますが、セルが浅ければ少ないインキが入りますし、深ければ多くのインキが入ることにより高精度な細密な再現性が得られます。インキの転移量を細かく調整できるので、非常にカラー再現にすぐれているという印刷手法です。
また、グラビアインキは一般的に油性インキが主流です。アルコールやトルエン、酢酸エチル等のインキ溶剤が使われています。最近は環境等の問題でトルエンを使用しないインキや、逆に水性のインキが出ていますが、基本的には油性インキになっています。
一般的に、プラスチックフィルムは濡れ性が悪く水を弾く性質があります。そういう被印刷体にインキをつける場合に、グラビアで印刷が向いている理由のひとつに油性の性質をもっているので付着性がいいことがあげられます。もうひとつは、カラー再現の中で細かな印刷がしやすいことがあります。
グラビア印刷を用紙に印刷する場合だと紙の表面は多少凹凸があるために、インキが付かなかったり付き過ぎたりすることがありますが、その点プラスチックフィルムへのグラビア印刷だと表面は非常に平滑性がありグラビアの版も表面が平らで窪みがあります。そういう意味では平らな面に平らな版をつけるということで大変適しているともいえます。
紙の場合はグラビアだとかすれぎみになることもありますが、平滑なフィルムはかすれることはありません。そういう意味ではグラビアの相性がいいといえるでしょう。
ルネッサンスの頃には、凸版木版画より利便性が高い凹版銅版画とされていたようで版画の世界で有名なエングレイヴィング(ビュランというノミを使って直接銅版を彫る技法)や、1513年にはドイツのグラーフによって銅を腐食して凹版とするエッチングが考案されています。エッチングは腐食液に耐えるグランド液を塗り、ニードル(針)で描画、腐食液で描画部分を腐食(エッチング)してグランドを除去します。その後、インキを詰めて非画線部のインキを拭き取り湿らせた紙に印刷します。現在は母材となる鉄の円筒をメッキして真円に研磨した後で、階調や濃淡を凹部をどのようにして表現するかによって製版を変えています。種類としては、前述のコンベンショナルグラビアや、網グラビアといった腐食による技法とダイアモンド針で機械的に銅シリンダーを直接彫刻してメッキ仕上げするヘリオクリッショグラフや、ダイレクトエッチングといった電子彫刻法があります。
また、偽造が難しい手彫刻による方法などもあり、他の版式とは非常に異なる特徴が凹版印刷にはあります。例えば、潜像凹版や微小文字、機能性インキが使われた偽造防止が可能なことから、紙幣や有価証券、芸術性の高い絵画などにも凹版が活躍しています。
フレキソ印刷
プラスチックフィルムの印刷をグラビア以外でやっているのがフレキソ印刷です。オムツとか生理用品でポリエチレン単体の袋、スーパーのお持ち帰りの袋などフレキソで印刷されているケースが多いでしょう。
単体の袋ではフレキソで印刷されるケースがありますが、複合されて貼り合わせされたラミネートものだと殆どグラビアです。
軟包装でもよくありますが、リピートでオーダーをいただく仕事が多いと、色合わせがとても重要でフレキソだと色ムラが出やすいといわれています。
版についても、フレキソは樹脂版をシリンダーに貼りつけて印刷するため、印圧の調整が微妙で、グラデーションも難しいかもしれません。
カラーカーブで0%から100%までリニアになればいいですが、フレキソの場合ハイライトの再現性が非常に難しく、インキが付いたり付かなかったりします。逆にベタ部ではインキがはみ出て太りすぎる傾向があります。
最近は版周りの進歩もあり、インキの転移量を微細に変えることもできますので以前よりは技術的に改善されています。しかし、グラビアと比較するとまだ印刷品質の差があり、顧客に満足してもらえないというのが現状でしょう。
孔版(シルクスクリーン印刷)
みなさんご存じのプリントごっこも孔版の原理が利用されていますが孔版印刷とは版にインキを付けて印刷するのではなく、版に穴をあけて、そこからインキを擦りつける方式になりますので多色刷りの場合は1色ずつ【印刷→乾燥】を繰り返すことになります。孔版で有名なものの1つに、シルクスクリーン印刷がありますが、以前は絹の上にインキをのせて非プリント部を乳化剤で覆いスキージと呼ばれる消しゴムのような物で擦って媒体の上にインキを落として印刷していたため頭にシルクが付いていました。現在は絹をあまり使いませんので単にスクリーン印刷と呼ばれることが一般的ですが、みなさん昔の名残でシルクと言われています。
現在は、100~300メッシュのテトロンや、ナイロンといった化学繊維、ステンレススチールの針金などで織ったスクリーンの目を用います。このスクリーンがステンシルと呼ばれる画像部が貫通した版になります。工程としては、アルミ材などでできた版枠に紗(しゃ)を張って乳剤をコーティングした後、透過ポジを貼り付けて、水銀灯で露光した後に現像して水洗いします。この露光されない部分が孔版となって、インキの転移部分になります。後はインキを枠内に入れてスキージ(ヘラ状のゴム板)で紗(スクリーン版・ステンシル)を上から加圧・移動させることによってインキは版膜のない部分を透過し、版の下に置かれた紙などの媒体に押し出されて印刷がされるといった仕組みです。
メリットは、印刷圧が低いためガラスやプラスチックはもちろん、樹脂や金属から布に至るまで大抵の素材に印刷できることが最大の魅力です。また、版面が柔軟に対応できるため平面に止まらず曲面にも印刷ができることやインキの種類が豊富であることに加え、インキ自体の層も凹版が十数ミクロン、平版のオフセットが1ミクロンの厚みであるのに対してシルクの場合は、5ミクロンから100ミクロンくらいの範囲で厚みを形成できることからTシャツに印刷をしたりCDのレーベルやガラスコップにも印刷できますし、最近では雑誌や販促物にも、シルクを使った視覚的効果に訴える印刷物をよく目にするようになりました。
平版(オフセット印刷)
現在、もっとも一般に使用されている印刷方式で版の形状は側面から見ると、平らになっています。平版はもともとドイツのゼーネフェルダーがケルハイム産の石灰石を使って楽譜の印刷用に凸版や凹版を試す過程で、この石灰石が多孔質で水分を保持する性質で脂肪を吸着することに気づき、脂肪性インキで字を書いて湿し水で湿して製版する現在の平版を発明したことにさかのぼります。この印刷の方法は、リングラフィー( リトグラフ)と呼ばれ、当時すでに盛んに行われていた凹版では表現されない味があり、その後多色刷りを含め広くヨーロッパ全土に普及しました。あの有名なロートレックの石版画もそのうちの一つになります。
また、ゼーネフェルダーは1817年に重たい石版石から亜鉛版を版材として使うことに成功しており、後の1903年にアメリカのルーベルがオフセット印刷を発明して、今日ある平版印刷の基礎が築かれました。
このオフセットとは凸版や凹版と違って紙が直接版に付くのではなく、ブランケットと呼ばれるゴムのシートにインキを転移させてから(オフ)、紙に印刷がされる(セット)ためオフセット印刷と呼ばれています。オフセット自体は、凸版でも凹版でも良いのですが平版が一般的に多く使われているため、正式にはオフセット平版印刷と呼ぶところをみなさん略してオフセットとかオフと呼ばれています。そこで凹版を使用するオフセット印刷は、通常のオフセット印刷と区別するため湿し水を使わないことから、ドライオフセットと呼ばれています。
このオフセット印刷に取り付けるする版(刷版)は平らなアルミの板で表面が前述の通り、水を含むように加工されています。これをレーザーで焼き付けて絵柄を形成するわけですが、焼き付けられた部分は水を保てなくなりますのでインキ(油)が転移されてしまう、それがブランケットに転移して紙にインキが移る、という流れになります。つまり、水と油が反発する原理を用いているわけです。
印刷機としては用紙を1枚1枚シートの状態で通す枚葉機と大きなトイレットペーパーのようなロール紙を高速回転させて印刷する輪転機の2種になります。どちらも一長一短があり枚葉機の場合は紙の種類や厚みの制約をあまり受けずに済むのですが輪転機(略してオフ輪と呼ばれています)はコート紙の場合で46/110kgベースまでの紙厚までしか通すことができず対応できる紙の種類も非常に限られています。また、インキが紙に転移された後にすぐ熱乾燥させるため、乾燥後の色の沈み加減(ドライダウン)がなく色合わせが枚葉と比べて容易で即加工に入れるといった高速性や廉価性がオフ輪にはあります。
また、機械の排紙側にシーターを付けてシート出しすることもできますが新聞折り込みなど袋裁ち(ギザギザカットで小さな穴があります)にして仕上げる場合は印刷と同時に加工まで仕上がった完成状態で出てきます。ただ、折り物などに前述の46/110kgベースなどを用いると、背中に割れが生じたり薄紙の場合でも熱乾燥により波打ちが出てしまうというデメリットがあります。
しかしながら折り込みチラシなど大量に印刷する場合は両面同時に刷り上げるオフ輪でなければ、実際のところ枚葉では対応できません。枚葉からオフ輪に切り替える通し数の目安としては、15000通し辺りからになります。B4チラシを例にしますとB2輪転でB4が4面(4丁と言います)のりますので最小ロットが6万部になります。
オンデマンド印刷
オンデマンドとはその名の通り必要なものを必要な時に必要な量だけ、という意味を指しています。印刷機も、その用途に応じてバリエーションが豊富です。代表的な印刷機のうち販促物に使う薄紙カラー印刷ならインディゴ社のEプリントとハイデルベルグ社のクイックマスターが有名です。Eプリントの場合は、完全な無刷版で色材もインキではなくトナーになります。出力解像度は、一般的な印刷が2400dpiであ無地網にムラが生じやすかったりするようです。ただし初期の”1000”の後継にあたる”2000”では、そのあたりもだいぶ改善されたようで、対象ロットはA4チラシで500枚くらいまでになるようです。
これに対して先のクイックマスターは、正確には有版のオンデマンド印刷機になり色材もトナーではなくインキのため見た目の仕上がりも普通のオフセット印刷と、遜色ありません。対象ロットは、A4チラシで1000~5000枚くらいのようです。また、これら以外の用途としてフィルムパッケージ向けのオンデマンド印刷機があります。従来、シリンダーのコストが高く展示会向けの小ロットには対応できる印刷機がありませんでしたが前述のインディゴ社が製造しているオムニアスというオンデマンド印刷機がこれを解決してくれます。
クオリティは、フィルムに印刷できるEプリントといった感じですがグラビア特有のトラッピング処理を施した白版がオンデマンドでも印刷できるというのは当時画期的だったと記憶しています。
高精細印刷
一般的な商業印刷物は、出力解像度が2400dpi(ドットパーインチ/1インチ角に2400個のドットが入るクオリティ)の、175lpi(ラインパーインチ/1インチの間に入るスクリーン線数が175本のクオリティ)になります。この、クオリティの中で、AMスクリーニングが適用されています。
AMスクリーニングは、先のマス目に網点が1つずつ入りその網点のサイズの大小で濃淡を表現します。これに対してFMスクリーニングという技術は微細な網点の数の大小によって濃淡を表現します。もちろん出力解像度も高くなり(容量が重たくなり)線数も増えます。だいたい、300線から多いものでは1000線を越えるクオリティまでありますがより綺麗でより高価になります。
ただ、FMの場合は平網や中間調にざらつきがでるといったデメリットがあり最近では、AMとFMそれぞれの利点を活かしたハイブリッドスクリーニング(あるいはXMスクリーニング)が評判になってきています。
コロタイプ印刷
網点を使わない印刷技法で刷版に感光性ゼラチンを塗布した10ミリくらいの厚みがある磨りガラスを使います。これを熱風乾燥して、表面にシワをつくりそこにインキが入るわけですが、絵柄はフィルムを露光して形成します。光が当たるとゼラチンが硬化して吸水性が悪くなることを利用して印刷する、この原理は平版と同じです。また、これにくわえて硬化の度合いで表面には凹凸ができますから水を吸わない凹部の皺に入るインキで印刷する原理は、凹版印刷になります。この、平版と凹版の合わせ技で印刷するコロタイプの弱点は対刷性の低い点にあります。1色でも500~700、カラーならマックス500枚くらいになります。ただし、美術館などに納める作品の複製には、保存用や展示用をあわせてもそんなにたくさん必要ないことやコロタイプ専用の流動性の低いインキは顔料が6割程度含まれていますが、その優れた耐光性からよく利用されています。
ハイファイ印刷
ハイデルベルグのハイファイカラーが有名です。通常のカラー印刷は減法混色であるC(シアン藍)・M(マゼンタ紅)・Y(イエロー黄)・K(ブラック墨)の4色を使って再現していますが、これに加法混色である、R(レッド赤)G(グリーン緑)、B(ブルー青)の3色を足して合計7色のインキを使って印刷する技術になります。当然ながら、再現領域は広くなりますから、従来のレギュラー4色では再現が難しかった写真などの仕上がり表現も、より豊かになります。また、レギュラー4色にオレンジとグリーンの2色を加えるヘキサクローム印刷などもあります。
ダブルトーン印刷
通常、モノクロを2色で再現する印刷を指します。例えば、墨と特色グレーを用いたり墨と藍で印刷します。モノクロ写真を4色分解して深みのあるカラーのモノクロ写真(リッチブラックは印刷物をルーペで覗くとわかります)とは異なりますが、スミ単色の場合と異なり2色で深みのあるモノクロが再現できます。(当然、その分コスト安くなります)また、場合によっては3色以上を使う場合もあります。
セキュリティ印刷(コピー防止)
紙幣などに適用されています。透かし入りの用紙や微細な文字を印刷して再現を困難にしています。一般的に偽造を防ぐためには「発見」と「抑止」の2つを押さえる必要があると言われています。これは、偽造を見抜くための発見と偽造防止が施されていることを認知させることで、行為そのものを断念させるための抑止を指しています。例えば、換金できる券などによく使われるサンドイッチペーパーがあります。破ると中間層に色が付いているため偽造を見抜くための特殊な用具が必要ありません。逆に、特殊な用具を必要とする偽造防止にはUV反応蛍光インキを使う印刷などがあります。真贋判定に必要な機材が入手困難なほど偽造が難しくなります。また、安易な複写を防ぐ印刷物として平網部分に、線数や網角を変えたパターンを入れることで、一見すると平網に見える部分がコピーをとると×印などが浮かんでしまう技術もあります。
電子透かし印刷(コピー防止)
画像にコピー防止のパターンを埋め込んだり、大手の印刷会社さんでは情報が含まれた透かしデータをチラシなどに印刷して、携帯電話とインターネットを利用する今までにはなかった新しいサービスを展開されています。
スクラッチ印刷
「scratch」とは引掻くという意味で、スクラッチ印刷は平版などで印刷された印刷物の一部分を銀色の特殊インキで覆い隠す印刷のことで主にスクリーン印刷が施されます。他に平版で印刷されるものもあります。
そして、覆い隠した銀色のインキの部分をコインや爪などで擦り取ると「当たり」「一等」「ハズレ」などの文字が表れるというもので、スピード宝くじ、キャンペーンの応募券、ファーストフード店のプレミアムカード等に使われています。
通常のインキは凹版印刷ではシンナー系や平版・凸版印刷では石油系のものが多く使われており、被印刷物との接着が強くなければなりません。しかし、スクラッチ印刷は後で擦り取れるようになっていなければなりませんので、シンナーや石油を含まないテレピン系を溶剤にしたインキを使用しており接着力が弱くなっています。これに透明インキとシルバーの粉末が混ぜられて隠蔽性をもたせています。
実際の印刷は、用紙に直接印刷してしまうと貼りついてしまい擦ったときにうまく剥がれないので、隠蔽したい部分にアンカーコート(OPニス)して、インキが貼りつきにくい状況をつくり、擦ったときにきれいに取れるようにしておきます。
また、カード等の印刷物で、スクラッチ印刷された部分を光に翳して見ると透けて見えたりすることがありますので、印刷物の裏面にはスミのベタ印刷をしたり、解答の文字に網をかけて薄くしておく必要があります。スクラッチ用のインキさえ用いれば何でも隠蔽できるわけではなく一定の制限があるということです。
もし、透けて見えてしまうがためにスクラッチ用のインキを厚く盛ると、インキは完全に乾いた状態にはなりにくく、そうすると印刷物の運搬時に擦れてスクラッチ用のインキが剥げてしまうことがありますので注意が必要です。
UVインキ印刷
通常、熱乾燥あるいは自然乾燥させるインキとは異なり、紫外線照射によって硬化するインキになります。この特性を活かして厚く盛ることができるシルク印刷に適用した面白い印刷が最近特に増えてきました。例えば、透明インキを厚く盛ったデコレート(クリアコートとも呼ばれています)は、水飴みたいな感じを絵柄にあわせて印刷できます。最近あまりお目にかかりませんが名刺の盛り上がり印刷もこれにあたります。点字も厚盛を活かした印刷になりますがシビアな精度を要求されるため専用のインキを使用します。また、透明インキにすることで、バリアフリーにもなります。あとは、視覚的効果に訴える疑似エッチング(リストールやリオトーンとも呼ばれます)や縮み印刷などがありザラついた金属的質感を得たり細かなシワよせができたりします。
蓄光インキ(光る印刷)
蓄光印刷とは光エネルギーを蓄える性質をもつ顔料を練りこんだインキにスクリーン印刷したものです。蛍光灯などの光を蓄えて暗がりで発光します。通常の蓄光インキは発光時間が30分~1時間程度ですが、7時間位発光するインキもあります。
フォトクロミック印刷(光る印刷)
フォトクロミック印刷とは、紫外線で可逆的に反応し、発色するフォトクロミック物質をマイクロカプセル化し、印刷したものです。この印刷は、紫外線の存在を色によって確かめることができるのが特長です。紫外線チェックカードは、フォトクロミック印刷を紙に施したカードで、太陽光に当てると、いままで無色であったチェック部がアオに発色します。肌に影響を与える紫外線の存在を可視的に確認できるので、化粧品会社の日焼け止め製品の販促品として使用されました。また、窓ガラスに貼ったUVカットフィルムとしても使われます。
ラメ印刷(光る印刷)
ラメ印刷とは、ラメ片を印刷インキ中(主にクリヤー)に混ぜ込んで使用インキとして印刷します。ラメ片を反射して通常の金属粉の反射とは全く違う変化に富んだ反射のしかたをします。ラメの種類としては金、銀、青、緑の単体とそれらを混ぜた7色に反射する物があります。
パール印刷(光る印刷)
パール印刷とは、可視光線をスペクトルに分ける効果があるパール粉をメジウム等に混ぜ込んでスクリーン印刷します。メタリック粉とは違うパール粉独自のわずかに7色に光を反射する効果が得られます。またパール粉の中には光の反射角度によって薄い黄色から薄紫、薄いオレンジ色から薄い青に変化する物もあります。
この2種類のインキは、インキの中に反射粉末を混ぜ込んでいるところに特長があります。
蛍光インキ(光る印刷)
蛍光インキを使用する印刷。蛍光インキは、可視光線および紫外線によって蛍光を発する昼光型顔料を用いたものです。ポスター、カタログ、パッケージ、その他誘目効果を目的とする用途で高彩度の印刷をするのに使用されたり、偽造防止の目的で、証紙類に刷りこんでおき、必要時に紫外線ランプで照らしてチェックする時などにも用いられます。
最近では、インキジェットプリンタで出力されるケースもあります。
フロッキー印刷・植毛印刷
フロッキー印刷とも呼ばれ、接着剤を塗布した紙やプラスチックに、静電気を利用して文字通り植毛します。かなり、インパクトがあります。
植毛(フロッキー)とは、手で触ると絨毯の感触が得られる静電植毛技術の応用です。
0.5mm~2.0mmくらいの短い繊維を静電気を利用して全体または部分に植え込み、触ると絨毯を敷き詰めたような手にやさしい感触を与えることができます。金・銀を除く殆どの色が使えます。紙、プラスチック、木材、ガラス、金属のも応用可能です。
工業用では、自動車の内装に使われることもあります。出版関係では、動物の絵本や芝生の部分に用いると効果がありそうです。
紙への植毛は、絵柄をオフセットで印刷し、植毛したい部分にスクリーンで「のり」を印刷してから、その「のり」の部分に短い繊維を静電気で付着させて植毛します。
立体物の場合は、植毛した部分のマスクを作り、「のり」をスプレーガンで吹き付け、その後短い繊維を静電気で付着して植毛します。
芳香印刷(マイクロセント)
インキに香りづけして、匂いのする印刷物になります。
一般的には芳香インキを使っています。この印刷を香料印刷(マイクロセント)といっています。
芳香インキは、インキ組成中に直接香料を加え、浸透乾燥タイプとして凸版などで印刷するタイプと、マイクロカプセルに香料を封じこめたものをインキ化し、印刷物自体は芳香性はありませんが、印刷面を擦ると擦過作用でカプセルが破壊され、芳香効果が生ずるタイプのインキがあります。
前者のタイプは保香性の問題などがあり今では殆ど使われておらず、後者が使われています。芳香インキは、まず香料メーカーが臭いをつくり、カプセルメーカーがインキに混ぜるための香料カプセルを作ります。このカプセルが通常のインキの顔料に替わるものなので、インキメーカーでカプセルとワニスを混ぜ合わせて香料インキを製造します。
通常インキメーカーでは数種類のカプセル(例えば、レモン、オレンジ、ラベンダー、等)を在庫しておりますが、印刷会社からの要望により独自の香りを作ることも可能です(もちろん限界はあります)。この場合、香料メーカーに特注しますので少し時間がかかります。
示温印刷(発砲印刷)
発泡剤を混ぜたインキを使うのですが、刷了後熱処理するとかなり膨らみます。
床材や壁紙、衣料など、さまざまなところで活躍しています。
バーコ印刷(発砲印刷)
バーコとは、アメリカのバーコ社が開発した隆起効果を出す印刷です。ポスターなどの印刷物に強調したい部分にメジウムを平版オフセットで印刷します。そして、メジウムの部分が乾燥しない間に、熱によって膨らむパウダーを印刷物の全面にかけてから粉を吸い上げます。そうすると、メジウムの部分にだけ粉が残り、加熱することにより印刷面の膨らませたい部分に付着したパウダーが溶解、膨張し立体的な印刷物ができます。
絵柄の立体感を表現するために、色のパウダーや透明のパウダーを選ぶなど、効果とコストを考えて効率のよいデザインを考えなければなりません。
線が細かいと弱いので、太めの線画でパウダーの付着面積を増やすことが必要です。ただし、広範囲のベタは、あまり効果がなく厚みにムラがでやすいので注意が必要です。
レンチキュラープリント(立体印刷)
レンチキュラープリントとは、微細なカマボコ形のプラスチックレンズを絵柄に貼り合わせて、立体像を見る方法です。断面がカマボコ形になっているレンズのことをレンチキュールといっており、それが均等なピッチで複数並んだものをレンチキュラーレンズといいます。レンズの厚みや1インチあたりのカマボコ形の本数などは何種類もあり用途ごとに厚みやレンズの線数も使い分けられています。
例えば、CDやDVDのジャケット・マウスパッド・ステッカー・トレーディングカード等によく使われていますが、表示されている人間の顔が正面から見ると笑顔、ちょっと角度を変えると怒った顔、別の角度から見ると寝顔になったりというようにいくつかのパターンに絵柄が変化するものです。
日本で最初にレンチキュラーが出たのは昭和30年代に流行したダッコチャン人形の開いたり閉じたりする目だったと言われています。
レンチキュラーには、平面に3次元空間のように表現する3Dと、見る角度を変えることにより絵柄が変化する2Dがあります。3Dは、左目と右目で違うものを捕らえるという目の視差を利用しています。2Dには、見る角度によって通常3つまでの絵柄が切り替わるるものと、一つの対象を4枚以上のバリエーションにした画像によって拡大縮小を表現するズームエフェクト、角度により被写体の中の物が移動するように見えるアニメーションエフェクト、角度により被写体の中の物が他の物に徐々に変化するモーフィングエフェクトがあります。
製造方法は、カマボコ形のレンズが万線状に並んでいるものに、例えばズームエフェクトを製造する場合、元画像で8画像(特に8画像である必要はない)違う画像で徐々に被写体の中の一部が大きくなる画像データを用意して、それを画像合成用のソフトに入れます。
そして、例えば75線レンズの場合、万線のレンズの方向と直角に切ると山ができ、75線だとそれぞれの山の幅が0.336~0.337ミリになります。(75線というのは1インチの中に山が約75個あるということです。)プラスチックの成型品なので冷えて固まるわけですから、製造ロットごとに誤差も生じます。
その8画像データを一枚にするには、正確なレンズピッチを仮に0.3364ミリとすると、レンズの裏側に8等分(0.3364÷8)した画像のラインを印刷することによって、ひとつのレンズの下に8つの画像を入れますが、1ミリあたり75本のレンズの下にそれぞれに8つに画像を分割することにより2Dや動きが表現されます。元原稿は原寸で300dpi以上の解像度があれば十分です。
レンズの線数は、10線から100線まであります。そのレンズ線数は用途によって使い分けなければなりません。レンズの線数ごとに焦点距離があり、どのくらいの距離からみたら一番ピントが合って見えるかということから使い分けなければなりません。レンズの線数が細かければ細かいほど、焦点距離が近くなります。そうすると、1インチあたり10本・20本の粗いほうが遠くから離れて見る大きいディスプレイに向いています。
手に持って動かすようなトレーディングカードやCDのジャケットやマウスパッドだと、75線が多く使用され、だいたい45センチくらいが焦点距離です。
あとは、ディスプレイの場所によってもレンズの材質を使い分けています。屋内だと通常はPETを使います。屋外だとアクリルが多いでしょう。
3Dホログラム(立体印刷)
3Dホログラムとは、平面画像と立体画像をまぜ、角度を変えると、虹色に変化するレインボータイプのホログラムで、平面上の画像と立体感を感じさせるバックの画像を組み合わせたものです。
ホログラムは転写箔とステッカーの2種類のタイプがあります。
例えば、その製造方法は、4倍の線画版下で入稿し、レーザー光を使って高解像力乾板に記録します。その後、メッキ方式で表面の微細な凹凸を金型原盤に再現します。ポリエステルフィルムの表面に金型原盤を用いて熱と圧力を加えてプレスした後、アルミ蒸着を施し、接着剤をコーティングすることによって転写箔またはシールを製造します。
なお、この場合の色は虹色のような分光であり、印刷方式ではないので、色指定や色の直し指示はできません。最大サイズは150×150mm。納期は2~3ヶ月かかるので余裕をもって発注したほうが良いでしょう。
クリヤー印刷(光沢を出す)
クリヤー印刷とは、印刷辞典には掲載されていませんがポスターなどの絵柄の中で特に強調したい部分にスポット的にUVインキ(透明インキ)でスクリーン印刷することを指します。インキにUVに反応する樹脂が用いられ、肉盛りがよく定着・乾燥が速いという特長があります。
効果としては、その部分に艶を出すことと耐擦傷性のために用いられ、ニス引き以上の効果をもちます。したかって、クリヤー印刷は、印刷というより実際は表面加工的な要素が強いといえます。
クリヤー印刷と同じような効果を出すやり方として、バーコ印刷やニス引きがありますが少し違います。
ニス引き(光沢を出す)
ニス引きは、全面に透明ニスをローラーでコーティングすることです。その後、ドラムに載せて熱乾燥させます。全面へのコーティングの他に、グラビア、平版オフセット、スクリーン印刷で部分的に艶をだすことも可能です。
そんなに光沢感はありませんが擦れやインキの裏移りなど印刷物を保護します。また、絵柄にあわせたコーティングが比較的安価にできます。
プレスコート(光沢を出す)
印刷物にニスを塗布した後、ステンレス製の鏡面版で熱圧着をすることで光沢がでます。部分的に施すこともできますがスポットの版代は結構高くつきます。
PP貼り(光沢を出す)
ポリプロピレンの略でグロスとマットがあります。部分的には施すことができません。カタログの表紙などに良く使われ、破れず水が付いても大丈夫なため耐久性や見た目はおすすめできますが最近は環境の観点では批判されています。
圧着加工
剥がせる糊を使って観音開きができる折り込みチラシを作ったり、二つ折りのハガキで プライベートな情報を守るDMなどができます。
型押し
雄型雌型の2つの金型を使って凹凸をつけます。
箔押し
金箔をはじめ、さまざまな色やホログラムなどの柄が入った箔を熱と圧で転写します。よく金ホットとか言われてます。通常、凸版の金型を使いますが凹版も使い分けて転写部分を盛り上げたり凹ましたりできます。
空押し
前述の箔押しを箔を使わずに凹凸だけつけます。
エーデルグラム(コピー防止)
エーデルグラムとは、特殊レンズシートを印刷物の画像の上に重ねると、印刷物の絵柄の中の隠し画像を浮かび上がらせる技術をいいます。かまぼこ形状の特殊レンズを用いてモアレ現象を利用しています。もともとは、株券・商品券・約束手形などの金券の偽造防止や認証用に用いるために大日本印刷㈱が独自に開発したものです。
基本的には、特殊レンズシートと印刷物がワンセットになって使用されて、今では出版向けに多く利用されています。
印刷版式は普通の平版です。以前は単色が主でしたが、カラー画像にも潜像として文字を埋め込んだらどうなるのかということで開発されました。ですが、実績がないのでこちらのほうはあくまでも理論上ということになります。
スクリーン角度の問題で、モアレが出る出ないというのがありますが、そこは出力機を調節しながらモアレがでないような状態で出力するということになります。
今後は、DMへの活用も考えられます。基本的にはDMを受け取った人がDMを持参してお店に行き、そこでレンチキュラーを重ねて確認してもらって懸賞になる等、来店を促すようなツールとしても考えられます。
また商品は模造されるケースがあります。模造される毎に刷り替えていたのでは、非常にコストが高くなってしまいます。こういうときに潜像を埋め込んでおけば、レンズをあてるだけで、自分のところのものだと確認できます。ランニングコストが安く簡単に検証できることになります。
本来は証券の偽造防止というところから出発したエーデルグラムですが、株券・商品券・約束手形などの金券には殆ど利用されていません。証券は機械で認識させることが多く、また見て分かるようなホログラムが印刷されています。
それに商品券を確認するのにレンチキュラーレンズを1個づつ店のレジに置くと、混雑時のお会計が大変効率の悪いものになりますので、日常生活で使うには向かないでしょう。
点字印刷
点字印刷とは、縦3点、横2点の6点の組合せからなる点字を触覚により読み取れるように、凸状の点を印刷でつくる方法です。
本や名刺だけではなく、最近では公共施設にも点字の案内板や触地図などが多く設置されています。点字は、触れることで、色々な情報を読みとる文字ですから、目で読む普通の文字と比べると制作上の制約もあります。
また点字には、文字の大きさや表記の仕方、1ページに入る文字の量や位置など様々なルールがありますので、企画の段階から視覚障害団体や点字の専門的知識のある製作会社やデザイナーとの打合せが不可欠です。
点字は拡大や縮小ができない文字です。大きくしたり小さくしたりすると、触ったときのザラザラ感が変わってしまい、読みにくくなったり、それが点字だと認識できなくなるからです。点字には、原則として一つのサイズしかないと考えて、制作にのぞまなければなりません。スペースがないからといって、縮小しておさめるようなことはできません。
点字は、私たちが普段使う一般の文字と表記も一部異なります。点字に対して一般の文字を「墨字」と呼びますが、墨字では、「彼は新宿へ行った」という文章の「彼は」の「は」、「新宿へ」の「へ」にみられるように、実際の発音と異なる表記を用いることがあります。しかし、点字では、こうした表記を発音通り「かれわ しんじゅくえ いった」と書くのです。
また、例えば「くうき(空気)」や「そうじ(掃除)」などのように、「う」で伸びる長音についても、「くーき」「そーじ」などのように、点字では横棒線の長音符号をを用いて書き表します。
点字を書く際には、マスあけのルールにも注意を払う必要があります。マスあけは「分かち書き」ともいいます。点字では漢字も一部使われていますが、一般にはカナ表記が殆どです。
通常、私たちが目にする「墨字」の文章は漢字カナ交じり文で書かれていますから「分かち書き」の必要はありません。しかし、これをすべてカナだけで書いたら、非常に読みにくいものになりますし、場合によっては意味を取り違える恐れも生じることになります。 この「分かち書き」のルールを正しく書くことは、点字についてかなり熟練しないと難しいといわれています。たとえば、「東京都」という語は、分けて書くことをしませんし、「都知事」という語も分けて書く必要はありません。ところが、「東京都知事」になると、分かち書きの必要がでてきます。これは「とーきょー」「とちじ」と分けるべきでしょうか?「とーきょーと」「ちじ」と分けるべきでしょうか?
点字は、表音文字なので、行末で自由に改行することもできません。分かち書きで区切られたひとかたまりの語句は、ひとかたまりで書かれなければならないのです。点字は、拡大、縮小ができないだけでなく、文字の間隔をちょっと詰めるということができませんし、こうした分かち書きの都合から点字の行末は揃いませんし、墨字に比べて1ページあたりに入る分量がとても少なくなることにも注意が必要です。
点字を書くときの難しさは、レイアウトの問題にもっともあらわれます。点字では、書体を変えて目立たせたりとか、文字を大きくして見出しにするなどというようなことはできません。レイアウトによる書き方の工夫でここは見出しだとか、強調されているとか、意味がわかれるなどとあらわさなければなりません。こうした書き方の工夫には、単に点字の表記に精通しているだけでなく、実際の視覚障害者のアドバイスが得られなければ難しいでしょう。
グーテンベルグと科学革命
グーテンベルグの印刷術の発明は、今まで優れた知識でも、人の目にふれることなく埋もれたいた学問を、印刷によって公表され蓄積され、継承される事で、学問の持続的発展が可能になりました。コペルニクス、ケプラーの天文学書が、活版印刷術のおかげで印刷され人々の手に届くようになり、学術書の理論の上に、ガレレオ・がリレーは、地球が太陽の周りを回っていると言う「地動説」を導き出して発表し印刷物として多くの人の知るところなりったことは有名な話です。活版印刷術の登場とその普及は、ヨーロッパ社会とその文化に多大の影響を及ぼした。特に、近代科学の成立「科学革命」に果たした「印刷革命」の役割は計り知れないものがあったと言われております。
科学ジャーナルの誕生
次に雑誌(科学ジャーナル)の発明について考えてみました。
1662年にチャールズ二世により設立されたロンドンのロイヤル・ソサエティ(英国王立協会)が、「ソサエティ」という科学雑誌(科学ジャーナル)を創刊したことです。
雑誌というメディアの登場は、今までの単行本を執筆するために必要な長い時間、出版社との面倒な交渉と多額の出版費用の工面といった苦労から、解放し、迅速で安価な費用で、研究成果の公表するネットワーク・システムを発明したことです。
科学雑誌に重要な要素ににはもう一つ「先取権」priorityという概念を生み出したことがあります。「第一発見者」単行本であれ雑誌であれ、自らが見出した新しい知識に対して、第一発見者としての権利=先取権を有する、という考えです。
これからの科学ジャーナルのゆくえ
近年ペーパーによる情報量が爆発的に増え情報管理は危機的状態になっていましたが、電子ジャーナルは紙に印刷された雑誌とは違い、コンピュータは記憶容量が大きく、大量の情報を蓄積して、必要に応じて情報を瞬時に検索して取り出せる。また、処理速度が早くなったコンピュータが相互に接続され、情報を交換・共有できるようになり、科学情報の大半は全てインターネット上で行なうようになりました。電子ジャーナルのインターネット上での学術的コミュニケーションが盛んになれば、publishということには、必ずしも「冊子体印刷」を含まないということも考えられます。